アルコール蒸散剤による食品の保存
アルコール蒸散剤とは
アルコールの殺菌力
アルコール蒸散剤を利用できる食品と水分活性(Aw)
アルコール蒸散剤封入用包装フイルム
アルコール蒸散剤のメーカーとその商品名
アルコール蒸散剤封入包装の設計手順
アルコールの老化防止効果
アルコール蒸散剤とは
食品のカビを防止するための包装技法として加熱殺菌注1、ガス充填包装注2、脱酸素剤封入包装注3などのほか、ワサビ成分の利用注4やエチルアルコール蒸散剤を封入する方法なども行われている。
エチルアルコール(エタノール、以後、単にアルコールと記述する)に微生物の増殖抑制や殺菌作用があるのは昔から知られており、生麺類、水産練り製品などにそのままで添加したり、ハムなどをアルコール溶液に浸漬したり、カステラ等の表面にスプレーしたりして保存剤として使用されている例は多い。
アルコール蒸散剤(アルコール鮮度保持剤、徐放性粉末アルコール製剤、アルコール揮散剤等とも呼ばれるが、ここではアルコール蒸散剤で統一する)もまた、このアルコールの殺菌力を利用したもので、アルコールを吸着させた担体(粉末)を小袋に入れ、アルコール蒸気が商品の包装系内に拡散して、カビを殺菌あるいは抑制するしくみになっている。小袋からアルコールが徐々に透過発散して、必要な期間、袋内のアルコール濃度を一定に保つことができるのが特徴である。
アルコールの殺菌力
アルコールの殺菌力は濃度により異なり、一般にアルコール4~8%でも静菌作用が認められるが、20%以下では殺菌作用はほとんどない。殺菌力が最も強いのは70%前後である。微生物の種類によってもアルコールに対する抵抗力が異なり、カビや細菌に比べると酵母類はやや抵抗力が強い。細菌についても、大腸菌に比べると乳酸菌の方が抵抗力がある。もちろん病原性大腸菌O-157に対しても殺菌力は十分にある。しかし、カビ胞子を殺菌することはできるが、細菌の胞子に対しては作用しないと言われている。
注1 マイクロ波、加熱水蒸気、乾燥熱風などで食品の表面を殺菌する方法。
注2 カビの生育に絶対必要な酸素を取り除き、不活性ガスの窒素や静菌作用のある二酸化炭素を袋内に充填する方法。酸化・変色防止、防虫などにも利用される。細菌や酵母による腐敗・発酵の防止は困難である。
注3 酸素吸収剤(脱酸素剤)の小袋を袋内に封入する方法で、鉄系、有機系がある。酸化止、変色防止、防虫などの効果もある。細菌や酵母による腐敗防止は期待できない。例:三菱ガス化学のエージレスなど
注4 わさびの成分である揮発性ワサビオイルを利用してカビや細菌の繁殖を防止する方法で、フイルムや紙に吸着させたもの、小袋になったものなどがある。ワサビ特有の臭気があるので用途は限定される。主として惣菜、弁当、鮮魚、精肉などの鮮度保持剤として利用されている。例:カラシード、ワサオーロ、ワサパワーなど
アルコール溶液の温度が高いほど殺菌力も大きく、5℃と18℃では殺菌力はかなり違ってくる。食品の食塩濃度が高いほど、PHが低いほど、食品の水分活性が低いほど殺菌効果は大きくなる。また、有機酸、グリシン、脂肪酸エステル等の添加で効果が大きくなることもわかっている。従って、アルコール蒸散剤を利用する場合もこのような要因を活用すればより大きい効果が期待できる。
蒸散剤からでるアルコール蒸気の殺菌力については、食品表面の静菌・殺菌が主となるので食品内部の酵母や細菌に作用しにくいという限界がある。食品表面については袋内ガス中のアルコール濃度 0.3~0.5Vol%でほとんどのカビを防止することができる。保存期間中、この濃度を保持するように設計すればよい。
アルコール蒸散剤を利用できる食品と水分活性(Aw)
アルコール蒸散剤の主目的はカビ防止であり、カビの生えやすい食品に用いられる。水分活性(Aw)の高い食品(例えば0.9以上)は、水分にアルコール蒸気が溶解して袋内蒸気濃度が十分に上がらないので、容量の大きい蒸散剤を使用しなければならず、それだけコストアップになる。逆にAwが低い食品(例えば0.8以下)では小さなものでよく、非常に有利である。使用方法は、乾燥剤と同じく、食品を包装袋の中に蒸散剤の小袋を同封する。表1に各種食品の水分活性を示した。
| 表1.各種食品の水分活性(Aw)の例 | |||
| 切り餅 | 0.990 | サラミソーセージ | 0.810 |
| お好み焼き | 0.980 | ジャム | 0.790 |
| 食肉 | 0.975 | しょうゆ | 0.760 |
| 焼きちくわ | 0.975 | 焼きまんじゅう | 0.850 |
| 魚肉ソーセージ | 0.970 | 羽二重餅 | 0.840 |
| ジュース | 0.970 | ダンゴ | 0.825 |
| タマゴ | 0.970 | つつみ焼き | 0.820 |
| はんぺん | 0.960 | ロールカステラ | 0.812 |
| かまぼこ | 0.960 | 甘納豆 | 0.800 |
| チーズ | 0.960 | フルーツケーキ | 0.790 |
| 食パン | 0.945 | いかくん | 0.780 |
| ふかしまんじゅう | 0.940 | マーマレード | 0.750 |
| 菓子パン | 0.920 | 最中のあん | 0.770 |
| ソーセージ | 0.900 | はちみつ | 0.750 |
| 一口だいふく | 0.895 | みそ | 0.740 |
| 茶まんじゅう | 0.890 | 珍味類 | 0.730 |
| ナガサキカステラ | 0.880 | ソフトさきいか | 0.710 |
| ようかん | 0.880 | 小麦粉 | 0.610 |
| パイ | 0.860 | にぼし | 0.580 |
| バウムクーヘン | 0.850 | チョコレート | 0.500 |
| ※上記の表は一例であり、包装される食品の正確なAwは実際に測定することが必要である。 | |||
アルコール蒸散剤封入用包装フイルム
カビを防ぐという効能は脱酸素剤と同じであるが、使用する包装材料が必ずしもKコートのようなバリヤー性フィルムでなくともよく、OPPのパートコート袋でも、OPP/CPPラミフイルムでも使用できるところが大きな違いである。したがって、包装材料費は安価におさまることが有利な点となる。さらに、脱酸素剤のように完全密封がどうしても必要であるということもなく、非常に小さなピンホール程度であれば防カビ効力に対する影響は少ない。一度アルコール蒸気が充満するとカビは死滅または増殖力をなくすため、アルコール蒸気が逸散してからも発カビはみられないことも多い。表2に各種フイルムのアルコール透過度を示した。
| 表2.各種フイルムのアルコール透過度 (単位:g/㎡・day,30℃) |
|
| EVA50 | 56.1 |
| LDPE50 | 19.0 |
| HDPE50 | 4.1* |
| CPP40 | 8.0 |
| OPP30 | 4.7* |
| OPP20/CPP30 | 2.0* |
| KOP20/CPP30 | 1.3* |
| ON15/LDPE40 | 7.3 |
| KON15/LDPE40 | 0.7* |
| PET12/CPP40 | 1.8* |
| KPET12/CPP40 | 0.9* |
| VMPET12/LDPE40 | 1.2* |
| OPP20/EVAL15/LDPE40 | 0.8* |
| *印がバリヤーフイルム ('84/8 FOOD PACKAGING P43) | |
アルコール透過度が10g以上のフイルムは使用しない方がよく、必要な袋内アルコール蒸気濃度を確保し、一定期間保存するには、アルコール透過度5g以下のフイルムが適当である。また、二重包装の場合は、内装にはアルコールをよく透過させる工夫をし、外装にはバリヤー性のよいフイルムを使用する必要がある。
アルコール蒸散剤封入包装の設計手順
図2には水分活性と必要アルコール蒸散剤の量を算出するグラフを示した。一般には次のような手順で大きさを決定する。
①包装形態、内容量、包装フイルムの決定
②食品の水分活性を測定する
③図から蒸散剤の必要量(食品100g当たり)を読みとる
④③で読みとった数字に内容量(g)/100gを掛ける
⑤実包試験で確認する。
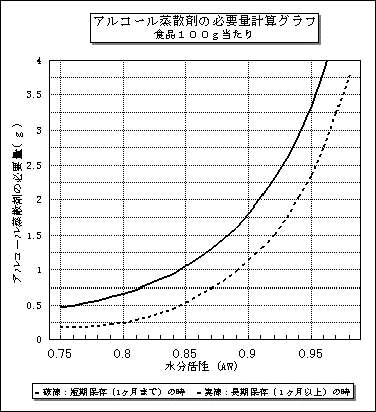
図2.食品のAwとアルコール蒸散剤の必要量
このように、アルコール蒸散剤は脱酸素剤とは違った特徴をもっており、使い方によっては非常に有用である。しかしアルコール蒸散剤にも欠点があり、エチルアルコール臭が袋内または食品に吸着し、食品によっては好ましくないことがある。このため、アンチモールドにバニラ香料を添加したり、アルコールに含まれる刺激臭成分を除去し、アルコール臭を軽減したものも発売されている。また、アルコールの臭気と食品の香りとが複合して異臭の原因になる、食品によっては退色・変色を促進することもある、酵素作用を阻害する、などの可能性もあり、採用するにあたっては事前のテストが必要である。
次に使用上の注意点として、蒸散剤の外袋を開封後1時間以内に使用すること、アルコールの蒸気は空気より重く、アルコール蒸気が行きとどくように配置を工夫し、食品の上部に置くほうがよい、食品の液体成分に接触するような置き方は避けることなどがある。食品外装の表示については、法的な表示義務はないが、誤食や誤解をさけるための表示をした方が安全である。
アルコール蒸散剤のメーカーとその商品名
現在市販されているアルコール蒸散剤はフロイント
産業㈱のアンチモールドとネガモールド、日本化薬㈱
のオイテック、上野製薬㈱のETパックなどがある。
アンチモールド102
最初に商品化したので高いシェアを持っている。吸着体には二酸化珪素(シリカ)を使用しており、アルコールを60~70%含有し、小袋フイルムを通して徐々にアルコール蒸気を放散する。一般用Fタイプ、バニラ香料を含んだVタイプがある。またアルコール臭の刺激成分を除去したものがマイルドタイプである。
ネガモールド
アンチモールドはカビの防止には威力を発揮するが、酵母による発酵、細菌による腐敗などにはほとんど効果はない。そこで脱酸素剤との併用で発酵、ネトの発生などを防止できないかとの考えが起こり、開発されたのがネガモールドである。脱酸素剤とアルコール蒸気発生の両方の機能を持っている。フイルムは脱酸素剤と同じく、バリヤー材を必要とする。
アルコール蒸散剤と脱酸素剤を併用するとアルデヒドなどの生成により刺激臭の発生が起こりやすいが、ネガモールドはこの問題も解決している。酵母、枯草菌の抑制には効果を期待できるが、すべての細菌に対して万能ではなく、過酷な環境における実包試験での確認を必要とする。
オイテック
吸着体に二酸化珪素を用い、含有濃度もアンチモールドとほぼ同じである。マイルドタイプもある。
ETパック
焼成雲母にアルコールをしみこませたもので、基本的にはアンチモールドやオイテックと同じである。しかし、含有アルコール量、蒸発速度、適正作業時間などを確認して使用することが必要である。
アルコールの老化防止効果
脱酸素剤はデンプンの硬化を促進するが、アルコールにはデンプンのβ化を遅らせる作用があり、カステラ、求肥、餅菓子などの硬化防止には有効である。アルコール蒸散剤を封入したものとしていないものとでは明らかに口あたりに差が生ずる。
