静電気防止フイルム
<はじめに>
小学校の頃、下敷きを脇の下で摩擦し、それを頭にかざして髪の毛を逆立てた経験があると思う。これは、下敷きを擦ることによって静電気が発生し、髪の毛を吸いよせる現象で、最も簡単な静電気の実験である。また、衣服の着脱時や車の降車時に経験するスパークも静電気である。では、静電気の正体は何か、どのようなときに生じて、包装にはどういう影響があるのか、どうすれば起こらなくできるのかなど、包装との関連について考えてみる。なお、静電気防止、静防、帯電防止、AS(Anti-Static)などは同義語として使用する。
<プラスチックと静電気>
ほとんどのプラスチックは絶縁体(電気を通さない)なので、基本的に、静電気が起きやすい物質である。
あらゆる物質は原子からできており、+(プラス)の原子核の外側に、-(マイナス)のいくつかの電子が軌道を描いて周り、A、Bの2つの物質が接触した場合、最も原子核から離れている軌道の電子がAからBに移る。これを剥がすとAは+に帯電し、Bは-に帯電する。この電子の移動が電気の正体である。
どんな物質でも瞬間には帯電するが、導電性の物質(金属や水-純水ではない)は帯電した電気をすぐに放出するので、静電気が残らないのである。
プラスチックの場合、電気を通さないので、発生した電気は逃げずにそのまま残り、導電性の物質と接触すると瞬時に放電する。帯電量が大きいとスパークになり、火花がでる。
<フイルムに静電気が発生する条件>
2枚のフィルムを合わせて、剥がすだけでも静電気は発生する。このとき押さえる力が強く、擦るほど静電気の量は多くなる。また、低温・乾燥時には、空気中に放電しにくいので、帯電がいつまでも続くことになる。
<帯電列について>
電子を放出しやすいもの、あるいは電子を受取りやすいものの序列を帯電列と呼び、異種の物質間で接触・摩擦が行われたとき、図2のように、正(+)に帯電しやすいものを上位に、負(-)に帯電しやすいものを下位にして並べたものである。
例えば、ガラス棒を絹布でこすると、ガラス棒は正(+)に帯電し、絹布は負(-)に帯電する。
帯電列上で近い位置にあるもの同士で接触・摩擦した場合は比較的帯電量が少なく、遠くなると帯電量も大きくなる。上部の物質が帯電しやすく、下位が帯電しにくいということではないので注意が必要である。この帯電列を知ることによって、効果的な静電気対策ができる。
ただし、物質の表面の粗さや、吸湿性によっては帯電特性に変化が生じる場合があるので、状況によって帯電列中の位置が変わることもある。
(+に帯電しやすいもの) ガラス ナイロン セロハン ビニロン 絹 アルミニウム 紙 スチール ポリプロピレン ポリエステル アクリル ポリウレタン ポリエチレン ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニリデン テフロン (-に帯電しやすいもの) 主な包装材料の帯電列
<包装フイルムと帯電性>
プラスチックのほとんどは絶縁体なので帯電しやすい。しかし、吸湿性フイルムが吸湿したり、導電性物質が表面にコートしてあると、静電気を放出しやすくなり、停電性は小さくなる。
△帯電しやすい包装材料
・OPP(二軸延伸ポリプロピレン)
PP樹脂自身は静電気をよく発生させるが、食品包装に使用されているラミネート用OPP、OPP/CPP共押出フイルムなどは静電気防止剤が配合されているので、極端な発生はない。けずり節などは両面コロナ処理の強静防タイプを用いる。マットOPP、KOP、PVAコートOPP、シュリンクPPにも静防タイプがある。
・CPP(未延伸ポリプロピレン)
CPPも静電気は発生する。粉末食品の包装には静防タイプのCPPを用いる。
・ON(ナイロン)
ナイロンは静電気が起きやすく、その帯電量も大きい。乾燥状態ほど帯電しやすい。
静防タイプのONもあるが、強静防ではなく、印刷時のヒゲ防止や、ON/LLの構成で米袋用として使用されている。
・PET(ポリエステル)
ポリエステル繊維が帯電しやすいのと同じで、PETフイルムも帯電性が大きい。
静防PETは、紅茶、ふりかけなどの粉末・微粒子の包装に利用されるが、湿度40%RH以下では静防効果はほとんどなくなるので注意が必要である。
KPETにも静防タイプがある。
・PE(ポリエチレン)、LLDPE、EVA
他のプラスチックと同じで、一般には帯電しやすい。粉末包装には帯電防止剤を配合した静防フイルムを使用する。ひねり包装用のOPEにも静防が要求される。
精密電子部品の包装には帯電防止剤(界面活性剤やカーボンなどの導電性物質)を練り込んだフイルムが用いられている。
・透明蒸着フイルム
アルミ蒸着フイルムと違い、透明蒸着フイルムは帯電しやすく、バリヤー性ばかりに気を取られて、静電気でトラブルになりやすい。
・紙
乾燥状態ではかなり強く帯電する。コピー時や印刷時、紙同士が剥がれにくいという現象はよく経験することである。
△帯電しにくい包装フイルム
・セロハン
セロハンの原料はパルプであり、性質は紙と同じで、乾燥時には帯電するが、一般使用時は保湿剤の配合によって水分調節をしてあるので帯電することはほとんどない。防湿セロハンやKコートセロハンも帯電性はほとんどない。
・アルミホイル
アルミニウムは優れた導電性を持っているので帯電しない。
・アルミ蒸着フイルム
アルミニウムは導電性なので、これを蒸着したフイルムも帯電性は非常に小さい。
△ラミネートフイルムの帯電性
アルミ複合フイルムやアルミ蒸着複合フイルムでは、ラミネートした状態でも帯電性は低いが、OPP/CPPの粉末包装ではOPP、CPPともに静防フイルムを使用することが多い。より大きい静防効果を期待する場合には強静防フイルムを両面に使用する。
以下、静防ラミネートフイルムの使用例を示す。
| フイルム構成 | 内容品の例 | 評価 |
| ON/AL/PE | 調味料 | ◎ |
| PET/VMPET/PE | コーヒー | ○ |
| 静防OPP/EVAL/静防PE | けずり節 | ◎ |
| 静防PET/静防CPP | 紅茶・お茶 | ○ |
| 静防OPP/静防CPP | にぼし | ◎ |
| PT/PE | 粉末医薬品 | ○ |
<包装における静電気の障害> 静電印刷、静電塗装、静電植毛、コピー機、空気清浄機、集塵機、静電発電機など、静電気を応用した技術も多くあり、すべて悪いことばかりではないが、一般の生活においては、静電気の印象は悪い。包装技術においても静電気はない方がいいのである。
△フイルム加工時
包装フイルムの加工工程は数多くあるが、特に有機溶剤を使用する印刷やラミネート工程でのスパークによる引火・爆発に警戒が必要である。引火物を扱う加工機械には、完璧な除電設備が要求される。
また、印刷時には静電気によってインキが引っ張られ、文字や柄のエッジにヒゲのような模様を描くことがある。
製袋時には袋をそろえにくく作業性が低下する。
△包装時
包装時の静電気障害としては、粉末の吸着や舞い上がりによるシール不良、フイルムの蛇行、空袋の付着などがあげられる。
給袋包装機では一枚一枚の袋の供給がうまくいかず、数枚が一度に運ばれることになる。
△店頭陳列
店頭陳列時にはほこりを寄せ付けやすく、外観が損なわれる。
△その他
電子部品などは静電気による断線や絶縁層の破壊による部品の不良が生じる。また、包装機にはマイコンの搭載が多くなったが、静電気によるコンピュータの停止や誤動作も考えられる。
<静電気の強さ評価方法>
△測定機
本格的な装置からハンディタイプまで、静電気関連メーカーからは多くの測定器が販売されている。
△灰吸着
フイルムをズボンなどの衣類で摩擦し、すぐに灰皿にかざして、灰の吸着量を観察するもので、実用に合った評価ができるので、広く行われている。
最も簡便な方法でありながら、最も直感的、実用的である。しかし、数値で表すことが難しく、あくまでも簡易的な方法である。
△表面抵抗値の測定
物質の表面抵抗値で帯電性を評価することが多い。一般に、PE、PP、PETなどの表面抵抗値は1015~17Ω程度である。この値が109Ω以下になれば障害は発生しないといわれている。
<静電気防止方法>
静電気防止対策がいろいろ考えられ、用途によって適切な方法が実施されなければならない。
△除電ツールおよび装置
・金モール、ブラシ
プラスチックは電子の移動がしにくいので、一部だけをアースしても除電できない。導電性のある金モールやブラシで全体を接触させアースする。比較的簡便な方法であるが、大きな効果が期待できる。
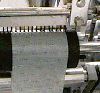
除電ブラシの装着例
・除電装置
高電圧を針状電極に加え、接地電極間でコロナ放電を起こしイオンを生成し、静電気を中和する電圧印加式除電器が代表的である。交流式、直流式がある。
・送風機
高電圧をかけて空気をイオン化し、送風機で帯電したものにあてて電気的に中和する。イオン化した空気を利用するので、帯電物と接触する必要はなく、凹凸のある帯電物にも効果的で、非常に便利なこともある。

春日電機製
△包装フイルム
・静電気防止剤の配合(内部改質法)
プラスチックに静電気防止剤(両性界面活性剤金属塩、イミダリン型両性界面活性剤など)を混合するもので、プラスチックの表面に静防剤がブリードしてはじめて効果を発揮する。
・静電気防止剤の塗布(外部改質法)
表面抵抗値が109Ω付近まで低下させるのに内部改質法では困難な場合、フイルム表面に静電気防止剤を塗布する方法が行われる。表面に十分な量を塗布できるので効果も確実である。
静電気防止剤の配合や塗布の場合、そのフイルムのラミネート強度、すべり性、シール性が変化することがある。また、安全性も十分に確認する必要がある。
△外気温度・湿度の調節
一般には低温であり湿度が低いほど静電気の帯電は多くなる。冬場ほど静電気によるトラブルが多いのも理解できる。
<参考になるホームページ>
http://www.ekasuga.co.jp/
http://www.sanynet.ne.jp/~simcoj/index.html
http://www.celles.co.jp/home.html
