環境ホルモンと包装材料
環境庁は2000年10月31日、スチレン類(スチレンの2量体、3量体)を、「現時点では安全と見なされる」と結論し、環境ホルモンリストからはずすことに決めた。(2000.11.6日本食糧新聞)
はじめに
この地球上で数多くの化学物質が製造、使用されており、その結果、世界規模での化学物質による環境汚染が広がり、最初は微量でも、それが食物連鎖により濃縮され、最終的にはわれわれ人間に取り込まれ健康上の影響を受けることになる。過去にはPCB、有機水銀、砒素などによる悲惨な事件があり、オゾン層を破壊するフロンガス(種類による)や最近のダイオキシン類による環境汚染は知らない人はいないほどの大問題となっている。そしてまた大きな社会問題になっているのが環境ホルモンによる汚染である。
- 環境ホルモンとは
環境ホルモンとは、正式には「外因性内分泌攪乱物質」といい、人および生物の体内に取り込まれて、あたかもホルモンのような働きをし、あるいはホルモンシステムを乱して、生殖異変、悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある化学物質のことである。
環境ホルモンが大きな社会問題になった発端は、平成8年1月にアメリカで出版されたシーア・コルボーン博士らによる「奪われし未来」(our stolen future)という本によって問題提起されてからである。この本の序文で、ゴア米国副大統領が、内分泌を攪乱させる作用をもつ化学物質が人および生物の生殖と発育という基本的な生物の生存条件に影響を与える可能性を指摘したことから、欧米で社会的関心が高まった。 - 環境ホルモンの影響例
今までに報告されている、環境ホルモンが原因とみられ、人や野生動物に対する異常な現象と考えられているうちの、数例を次に示した。
①低孵化率や奇形の多いハクトウワシ(北米五大湖、PCBまたはDDTの可能性)
②オスのペニスが矮小化したり、卵の孵化率低下、個体数減少がみられる湖のワニ(フロリダ州、DDT、有機塩素系農薬)
③ひな鳥の8割が孵化する前に死んでしまったり、メス同士が「つがい」になるセグロカモメ(北米五大湖、DDTの可能性)
④精巣停留や精子数減少等によって生息数が激減したピューマ(アメリカ、DDTやPCBが原因か)
⑤雌雄同体のニジマスが多く発見された(イギリス、工業用化学洗剤に含まれるノニルフェノール) - わが国における取組み
わが国においても、日本近海の巻貝の一種であるイボニシには雄性化や個体数の減少がみられ、船底塗料や漁網の防腐剤として使用されている有機スズ化合物が原因ではないかと考えられている。また、多摩川のコイにも生殖異変が起こっており、洗剤などに使われている界面活性剤のノニルフェノールの影響ではないかという報告もある。
環境庁においては、環境保全行政上の新たで重要な課題ととらえ、平成9年3月に、専門家からなる「外因性内分泌攪乱物質問題に関する研究班」を設置し、調査研究が始まった。同年7月には、中間報告として、内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質、つまり、環境ホルモンとして67品目の化学物質と、カドミウム、鉛、水銀も含めて70品目を挙げている。
これらの化学物質のうち、40種類以上は農薬の有効成分であり、既に生産・使用が中止されたり、わが国では使用実績のないものも多い。比較的よく知られている物質として、ダイオキシン類、PCB、DDTなども含まれている。食品包装材料も無関係ではなく、注目されているのは次の3つである。
・ビスフェノールA(ポリカーボネートやエポキシ 樹脂の原料)
・フタル酸エステル類(ポリ塩化ビニル等の可塑剤)
・スチレンの2量体、3量体(ポリスチレンに含まれる) - ビスフェノールA
ビスフェノールAはポリカーボネートやエポキシ樹脂の原料として使用されている。ビスフェノールAの内分泌攪乱作用については、現在までのデータや報告から推測すると無視できない。しかし、その作用は非常に弱く、樹脂からの溶出量もはるかに微量なので、人に対する影響はないのではないかと言われている。
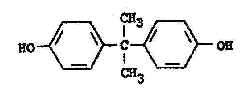
ビスフェノールA
- ポリカーボネート(PC)
ビスフェノールAと、塩化カルボニル又はジフェニルカーボネートを重合して得られる。透明性に優れた非常に硬い樹脂で、優れた機械的性質と耐熱性をもっている。煮沸殺菌ができるので哺乳瓶、食器類(給食を実施する公立小・中学校のうち40%の学校でPC製の食器を使用しているという)、コーヒードリッパーなどに使用されている。食品包装用フイルムとしては、防虫性や耐熱性が要求される成形容器に一部使用されるぐらいで、ほとんど使われていないと言ってもよい。ガスバリヤー性、防湿性は悪く、酢エチやトルエンなどの有機溶剤に溶ける欠点がある。食品包装および容器関係では他の材質への代替は可能である。
食品衛生法に基づくPCの規格基準では、ビスフェノールAの溶出限度は2.5ppm、材質基準では500ppmとなっている。
食品用途以外ではコンパクトディスク(CD)、車のランプカバー、OA機器などに使用されている。
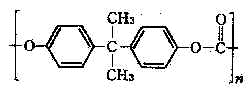
ポリカーボネート
- エポキシ樹脂
接着剤などに使用されているエポキシ樹脂もビスフェノールAを原料としており、食品関係では缶詰内面の腐食防止のためのコーティング剤として使用されている。製缶業界ではエポキシ樹脂を使用しない方向で検討を進めている。
- ポリスチレン(PS)
エチレンモノマーとベンゼンからエチルベンゼンを介してスチレンモノマーをつくり、これを重合する。ポリスチレンのクリアーなフイルム(GP)は硬くて脆い。耐衝撃性を向上させるためにゴム系樹脂をブレンドしたハイインパクトPS(HIPS)や、延伸したポリスチレン(OPS)もある。ガスバリヤー性、水蒸気遮断性ともに悪い。また、有機溶剤に溶けやすい。
ポリスチレン(PS)といえば、一般には成形用樹脂として大きな需要をもつ。加工が容易なことから食品用トレー、弁当パック、コップなどの包装用、冷蔵庫などの電気製品、おもちゃ、プラモデルなどに使用されている。発泡ポリスチレンは緩衝材や建材(断熱材)、カップラーメンの容器などとして利用されている。フイルムとしては、ガス透過性が大きいので呼吸する野菜・果物などの包装に適しており、鮮度保持フイルムとして利用されている。また、透明性を生かしてカートン、窓付封筒などの窓部分、シュリンクラベルにも使用されている。
材質中の揮発性物質の基準は、一般の食品容器 5000ppm、発泡ポリスチレン(熱湯を用いるものに限る)はスチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、n-プロピルベンゼンの濃度の合計が2000ppm以下、かつ、スチレン及びエチルベンゼンの濃度がそれぞれ1000ppm以下 、但し、油性食品用については5000ppm以下となっている。抽出液の蒸発残留物は30ppm以下である。
ポリスチレンの環境ホルモン問題としての焦点は、スチレンダイマー(2量体)とトリマー(3量体)である。スチレンダイマーはスチレン分子が2個くっついたもの、トリマーは3個くっついたもので、ポリスチレンの中に含まれている。これらが本当に内分泌攪乱作用があるのか、これらの物質がどれだけ溶出してくるのかが問題になっている。特に子供、幼児、妊婦なども利用するカップラーメンの発泡スチレン容器が問題になっており、日本即席食品工業協会では独自に分析し、ダイマーには女性ホルモン作用はないと発表している。しかし、データはまだ少なく、絶対に安全だという確証がない以上、いつまでも問題視される可能性もある。はっきりした結論がでるまでにはさらに時間が必要である。
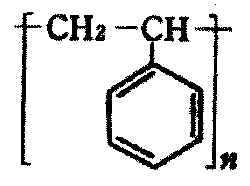
ポリスチレン(PS)
- ポリ塩化ビニル(PVC)
アセチレンと塩化水素を、触媒を用いて反応させ塩化ビニルモノマーを合成し、これを重合させる。製法はこのほかにも数種類ある。 PVCの種類には軟質と硬質があり、それぞれにフタル酸エステル類の可塑剤が添加されており、軟質のほうがより多い。軟質フイルムは伸び、引裂強度が大きく、強靭なフイルムであるが、すべり性が悪く、腰もないので使いにくい。業務用のストレッチフイルムに使用されている。ガスバリヤー性、防湿性ともにあまり良くない。硬質塩ビのシートは成形性がよく、食品用のトレイや容器、ブリスターパックなど、収縮塩ビとしてシュリンク包装、ラベルやキャップシールなどに使用されている。食品用途の塩化ビニルの可塑剤として用いられるフタル酸エステルのほとんどがフタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)である。 塩ビの食品用途以外の主な用途は、ビニールシート、農業用ビニールシート、建材等である。また、(社)日本玩具協会によると、おもちゃのうち、歯固め、おしゃぶりには、1社を除き、ポリ塩化ビニルは用いられていない。
溶出に関する基準値(基本となるもの)は、蒸発残留物(総溶出物)30ppm以下(0.06mg/c㎡)となっている。
ポリ塩化ビニルは、塩ビモノマーや添加剤の発ガン性、酸性雨、ダイオキシンに続いて環境ホルモン問題でも矢面に立たされ、食品包装用途縮小の傾向は今後も続くと思われる。
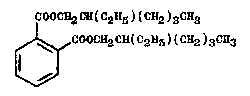
フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)
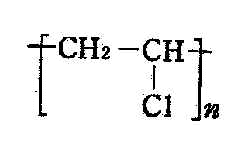
ポリ塩化ビニル(PVC)
- まとめ
環境ホルモンの恐ろしさは、きわめて微量でも、精子数減少などの生殖機能障害、悪性腫瘍等を引き起こし、特に胎児期や幼児期に影響を受けやすいという特徴があり、数十年後には生物生存の危機をもたらしかねないという点にある。また、環境ホルモンの疑いのある物質約70種類について、本当に内分泌攪乱作用があるのか、どのようなメカニズムで攪乱作用が生ずるのか、どの程度の摂取量でどのような症状がでるのか等について、今後の調査、研究を待たなければならない。さらに、作用や影響の測定方法も確立していない現状で、環境汚染状況の把握、科学的知見の充実、環境リスク管理などこれからの課題は多い。
なお、ホルモンの働き、環境ホルモンの疑いのある約70種類の物質名、毒性、環境汚染、溶出試験等の報告例、我が国の今後の取り組み等については環境庁のホームページに記載されている。
関連ページにジャンプ→ 環境省
